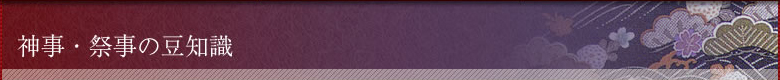歳旦祭
歳旦祭
歳旦祭は1月1日に行われる祭儀で、年の始め、月の始め、日の始め、即ち1月元旦に行われるのでそう名付けられている。宮中に於いては、小祭式を以て三殿に祭儀を執行、天皇陛下は四方拝を行われ御玉串を皇祖の御前にて奉奠される。この日、神宮、全国神社に於いても中祭式を以て祭祀を奉仕する。
 節分祭
節分祭
節分は一年を春、夏、秋、冬の季節に四等分して立春、立夏、立秋、立冬と次の季節に移るときのことをいうのですが、いまは立春の前夜だけに名が残っているのは、やはり春を待つ気持が強いからでしょう。毎年二月二、三日ごろにあたり、多くの行事がありますが、なかでも知られているのは追儺(ついな)です。追儺の儺は鬼に扮した人のことで、鬼遺(おにやらい)ともいい、鬼を払って福を呼びこもうとするものです。
 大祓神事(おおはらいしんじ)夏越の祓(なごしのはらえ)
大祓神事(おおはらいしんじ)夏越の祓(なごしのはらえ)
大祓(おおはらえ、おおばらい)、夏越(なごし)、六月祓(みなつきはらい)、荒和の祓(あらにごのはらい)ともいい、旧暦六月晦日におこなわれる。古代律令体制以来、6月、12月の晦日に宮中で大祓が行われ、また民間の神社においても6月、12月の大祓は盛んにおこなわれた。しかし、時代は下がりいつの頃からか12月の大祓はすたれ、もっぱら6月の祓いだけが盛んになりこれを夏越の祓と呼ぶようになった。この夏越神事では茅輪(ちのわ)くぐりが一般的で、神社の鳥居の下や拝殿の前などに茅(ちがや)を束ねて大きな輪を作ったものを設けて、宮司に続き一般参拝者もくぐり罪穢れや災疫いを祓う。『公事根源』などには、輪をくぐるときに「みな月の夏越の祓する人はちとせの命のぶといふなり」という歌を唱えると伝えている。
 七五三詣
七五三詣
男女3歳を髪置、男児5歳を袴著、女児7歳を帯解といい、これらの年齢に相當する男女児が盛装して、11月15日に神社へ参拝し、神の御加護によりこれまで成育したことを感謝し、併せて神と人との分離(男女とも7歳までは神である)を報告し、家庭人としてさらに社会人としての教養をなす事を誓うのである。この儀式は、大昔には日取りも一定していなかったが、現在のごとく11月15日となったのは、天和元年に徳川将軍綱吉の子徳松君を、この日に祝ったのが例となったと伝えられている。
 神棚
神棚
日本人にとって神さまとは、決してかけ離れた存在ではなく、私たちの日常生活の中にすみずみまで溶け込んでいる、身近で親しい存在です。家庭に神さまをおまつりすることで 、我々は神さまのおかげに感謝する心を養いやさしさや思いやりの心を育んできました。
たとえば、田舎の旧家などに、台所や門口、竈(かまど)には竈神(荒神・こうじん)さま、井戸には井戸神さま、納戸(なんど)には納戸神さま、トイレ・厠(かわや・お手洗い)には厠神さまというふうに いろいろなお神札(ふだ)が貼ってあったり、お供えものがしてあったりするのを見かけたことのある方も多いでしょう。
このように、日本人は昔から家のいろんな場所に、さまざまな神さまをごく自然にまつってきたのですが、それは、いずれも私たちの生活に欠かすことのできない、大切な場所であったからです。
日本人にとって、神さまとともに生活を営む中で、いつも家に災いがなく、家族がみんな元気で暮らせるように祈り、日々のお恵みに感謝することが日本人の暮らしぶり生活そのものだからです。
 神葬祭
神葬祭
今日、葬儀の多くは仏式で営まれています。このことは、江戸時代に入って寺請制度(てらうけせいど)のもとで、仏式による葬儀が一般化したことによります。しかし、江戸時代には、日本古来の葬儀のあり方を見直す運動が起こり、明治時代になって神道式による葬儀を行うことが一般に認められるようになりました。
神道式の葬儀を神葬祭(しんそうさい)といい、日本固有の信仰をもとに整えられた葬儀式です。厳かで儀式もわりやすく、しかも質素なことから、今日では神葬祭が増える傾向にあります。
神葬祭の主な行事
- 帰幽奉告(きゆうほうこく)・・・故人が亡くなった旨を氏神さま、神棚、御霊舎に奉告(ほうこく)します。
- 納棺の儀(のうかんのぎ)・・・遺体を柩(ひつぎ)に納めます。
- 通夜祭(つやさい) ・・・夜を徹して故人の御霊を慰めるおまつりです。
- 遷霊祭(せんれいさい) ・・・故人の御霊を霊璽(れいじ)と呼ぶ白木の「みしるし」に遷し留める(うつしとどめる)おまつりです。
- 葬場祭(そうじょうさい・告別式)・・・人に最後の別れをするおまつりです。
- 火葬祭(かそうさい)・・・火葬に付す(ふす)際のおまつりです。
- 埋葬祭(まいそうさい)・・・遺体・遺骨を埋葬するおまつりです。
- 帰家祭(きかさい)・・・葬儀が滞りなく終了したことを霊前に奉告するおまつりです。
- 清祓(きよはらい)・・・五十日祭を終え家中を祓います。そして、神棚のおまつりを再開します。
- 百日祭・・・亡くなってから100日目に行います。
- 命日・・・毎月、毎年巡ってくる亡くなった日に故人を追慕します。
- 年祭(ねんさい)・・・満1年、2年、3年、5年、10年、以下10年ごとに行い、50年の次は100年、以下100年ごとに行います。
 霊璽(れいじ)
霊璽(れいじ)
霊璽は位牌にあたるもので、御霊代(みたましろ)ともいわれます。神葬祭では、戒名にあたるものがありません。故人につける神道の霊号には、その徳をたたえる意味もありましたが、今日では名前の下に「命(みこと)」、男は「大人(うし)」「彦(ひこ)」、女は「刀自(とじ)」「姫(ひめ)」等をつけることが一般的です。霊璽の表面には霊号(れいごう)が、裏面には「何年何月何日帰幽享年何歳」などが墨書されます。